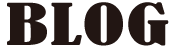ミニトマトの葉先枯れ対策
先週開催した酵素の世界社大中支部の現地研修会でミニトマト生産者圃場を訪問した際、葉先枯れの対策はどうしたらよいか?という話になりました。
実際に訪問した2件の圃場では全体的に葉先枯れが出ている状態でした。

葉先枯れは品種によっても差がありますが、水不足やカリ不足、植物体内の糖と窒素のバランスの崩れ(アンモニア態窒素の滞留)等が主な原因です。
島本バイム農場ではほとんど葉先枯れが出たことがない、と伝えるととても驚かれました。
ぜひ見に行きたいということで早速ミニトマト部会の皆さんが視察にいらっしゃいました。
現在バイム農場では8月30日に定植したCF千果(台木キングバリア)を栽培中です。
今季のハウスミニトマトの周年(越冬)栽培では、定植以降年内は平年よりも高温で推移し、根張りが弱い状態のまま厳冬期に突入したケースが多いと思います。
さらに厳冬期中はハウス内過湿による病気の発生やミニトマト果実の割れを抑制するため、潅水量を控えがちになります。
根張りが弱く、潅水を控えがちになる状態では葉先枯れの原因となる水不足や、カリ不足(土壌にカリがあっても根張り・根の活性が低い状態では吸収できない場合もあります)にますます陥りやすくなります。

バイム農場では11月のハウス夜温を低く管理することで夜間の根への糖の転流を促し、しっかりと根を張るようにしました。
そして厳冬期も潅水量を絞ることなく、根の活性を落とさないように努めました。
また、定植以降潅水の際は毎回トウゲンや拡大バイエム酵素液を入れることで、草体内で糖と窒素のバランスが崩れないようにしています。
圃場の土質(保水力や水はけ)によっては潅水量を増やすことには限度がありますので、やはり良質堆肥の施用による土づくりによって土壌の保水性と排水性を高めることは必須です。
11月の夜温の低温管理で厳冬期を乗り切れる根張りを確保し、厳冬期中も積極潅水を行うことで冬期の収穫量を落とさず、糖の潅水・葉面散布で窒素の消化を促すとともに食味も向上でき、結果として葉先枯れも出にくい状態に出来ているのではないかと推察しています。
実際のミニトマトの状態やベッドの濡れ具合、ミニトマトの味を確認していただき、とても勉強になったと言っていただきました。
品種による差もあるため、バイム農場でも来季は大中地区で栽培されている品種をはじめ複数品種で試験したいとも考えています。
またいつでも圃場を見に来ていただきたいですし、こちらも見に行きたいと思います。
土づくりや作物栽培に関するお悩みがありましたらいつでもお問い合わせください。
島本バイム農場
山添