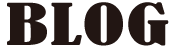琵琶湖のヨシの有効活用-堆肥化で期待される効果
ヨシの有効活用についてご相談を受け、滋賀県の内湖・西の湖を訪ねてきました。
西の湖には近畿で最も多くのヨシが自生しており、琵琶湖の水質浄化や生き物たちのすみかとして、非常に重要な役割を果たしています。

冬になると、地域では毎年ヨシ刈りが行われ、乾燥させたヨシは茅葺き屋根の材料などに利用されています。
しかし近年では、その需要が減少傾向にあり、刈り取り後のヨシの行き先が課題となっています。
ヨシ原の健全な生態系を維持するためには、冬季の刈り取りによって新芽の成長を促すことが欠かせません。
刈り取りを怠るとヨシ原が荒廃し、良質なヨシが得られなくなってしまいます。
そのため、需要が減っている現在でもヨシ原の管理は継続が必要であり、過剰となったヨシの有効な処理・活用方法が求められています。
そこで、今回弊社ではヨシを活用した堆肥化を進めています。


ヨシは稲わらと比べてケイ酸を多く含んでおり、水田などとも相性が良いことが特徴です。
また、木材を原料とした堆肥に比べ、短期間で堆肥として利用できる点も利点です。
1年で4メートルほど伸びるヨシには植物ホルモンも多く含まれているのではないかと考えられ、それらの効果も期待したいところです。
実際の仕込みでは、発酵開始から翌日には60℃、翌々日には80℃近くまで温度が上昇しました。

その後、1回目の切り返しを行い、1週間後に2回目、さらに3週間後に3回目の切り返しを実施し、そして、一定期間馴染ませてから堆肥として完成させる予定です。
ヨシの有効活用を通じて、地域の環境保全や水質浄化、生物多様性の維持などに貢献できればと思います。